長期優良住宅とは

HOMEくん、今日は「長期優良住宅」という特別な住宅について学ぼう。

長期優良住宅って何ですか?

長期優良住宅とは、長く使えるように特別に設計された家のことだよ。この家は耐久性や耐震性が非常に高く、環境にも優しい設計がされているんだ。

性能が高いのはいいことだと思いますが、長期優良住宅と認定されることでどんなメリットがあるんですか?

大きなメリットは、税制優遇や低利の住宅ローンを利用できることだね。これによって、購入や建築のコストを抑えることができるよ。また、長期的に見てメンテナンスコストも低く抑えられるから、経済的にも大きな利点があるんだ。

デメリットはありますか?

デメリットとしては、認定を受けるために初期に高い建築コストがかかることがあるね。また、認定を保持するためには定期的な点検やメンテナンスが必要で、これが長期的にはコストがかかることもあるよ。さらに、初期の固定資産税が軽減されるものの、時間が経過すると税率が上がることもあるんだ。

どんな基準があるんですか?

長期優良住宅には、いくつかの重要な基準があるよ。例えば、耐震性能は耐震等級3を満たす必要があるし、省エネ性能も高い基準をクリアしないといけない。また、バリアフリー設計や居住環境の良さも評価されるんだ。

申請はどうするんですか?

申請するには、設計段階での計画をしっかりと立てて、建築基準に適合していることを証明する必要があるよ。大体の場合はハウスメーカーの人が代行してくれるけどね。完成後は専門家による検査があり、すべての基準を満たしていることが確認されたら、認定が下りるんだ。

長期優良住宅は、将来にわたって快適で安全な生活を送るための素晴らしい選択肢だよ。環境に配慮しながら、長く愛される家を建てたいと思う人には特におすすめだね。

それにしても「家づくりの用語」って難しい。

まあ、専門用語が多いですからね〜。

こういうの、初心者にも分かりやすく教えてくれるサービスないんですか?

あ〜、それなら「LIFULL HOME’S 住まいの窓口![]() 」ですね。
」ですね。

え?あるの?

無料で、オンラインも対応なのでどんどん活用しちゃって下さい。

先生、それ早く言ってよ〜。
長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態で使用できるように、構造や設備に関する措置が講じられた住宅のことを指します。この制度は、住宅の長寿命化を促進し、安全かつ快適な住環境を提供することを目的としています。
長期優良住宅の特徴
- 長寿命化: 長期優良住宅は、耐久性や耐震性に優れ、長期間にわたって良好な状態を保つことができます。
- 環境配慮: 環境に配慮された設計がなされており、エネルギー効率の高い住宅となっています。
長期優良住宅のメリット
- 税制優遇: 長期優良住宅の購入や建築には、税金の控除や補助金などのメリットがあります。
- 低利の住宅ローン: 長期優良住宅を建築する際には、低利の住宅ローンを利用することができます。
長期優良住宅のデメリット
- 建築コスト: 長期優良住宅の認定基準を満たすためには、通常の住宅よりも高い建築コストがかかることがあります。これは、耐震性や省エネルギー対策などの高い性能を実現するための追加投資が必要だからです。
- 定期点検・メンテナンスコスト: 認定を受けた後も、長期優良住宅の基準を維持するためには定期的な点検やメンテナンスが必要です。これにより、長期的に見ると維持費用が増加する可能性があります。
- 固定資産税の増加: 長期優良住宅の認定を受けると、初期の数年間は固定資産税が軽減されますが、その後は固定資産税が増加する可能性があります。特に、評価額が30万円の場合、3年後には50%の軽減措置がなくなり、固定資産税が増加します。
長期優良住宅の認定基準
長期優良住宅の認定を受けるためには、国が定める一定の基準を満たす必要があります。これらの基準は、住宅の耐久性、安全性、快適性を高めることを目的としています。
性能項目: 認定基準には、劣化対策、耐震性、メンテナンスや更新の容易さ、適応性、バリアフリー設計、エネルギー効率、居住環境、単位面積、維持計画などの9つの性能項目
- 耐震性: 地震に強い構造であること。特に、耐震等級3の基準を満たすことが求められます。
- 省エネ性能: 省エネ基準を満たし、エネルギー効率の良い住宅であること。
- メンテナンスのしやすさ: 定期的なメンテナンスや更新が容易であること。
- バリアフリー設計: 高齢者や障害者も生活しやすい設計であること。
- 居住環境: 良好な居住環境を確保していること。
- エネルギー効率: エネルギー効率基準は、省エネ法に規定されるエネルギー効率基準、次世代省エネ基準に適合することが求められます。また、熱性能等級5以上(UA値、ηAc値、結露防止)および一次エネルギー消費等級6を達成することが必要
などです。2022年10月1日から、既存の住宅に対する認定基準の改訂が行われました。これには、壁量計算による耐震性能レベル3の判定の見直しや、省エネ基準の改訂などが含まれます。
長期優良住宅は、その名の通り、長期にわたって良好な住環境を提供することを目指した住宅です。税制優遇や低利の住宅ローンなど、多くのメリットがありますが、購入や建築を検討する際には、メリットとデメリットをしっかりと考慮することが重要です。
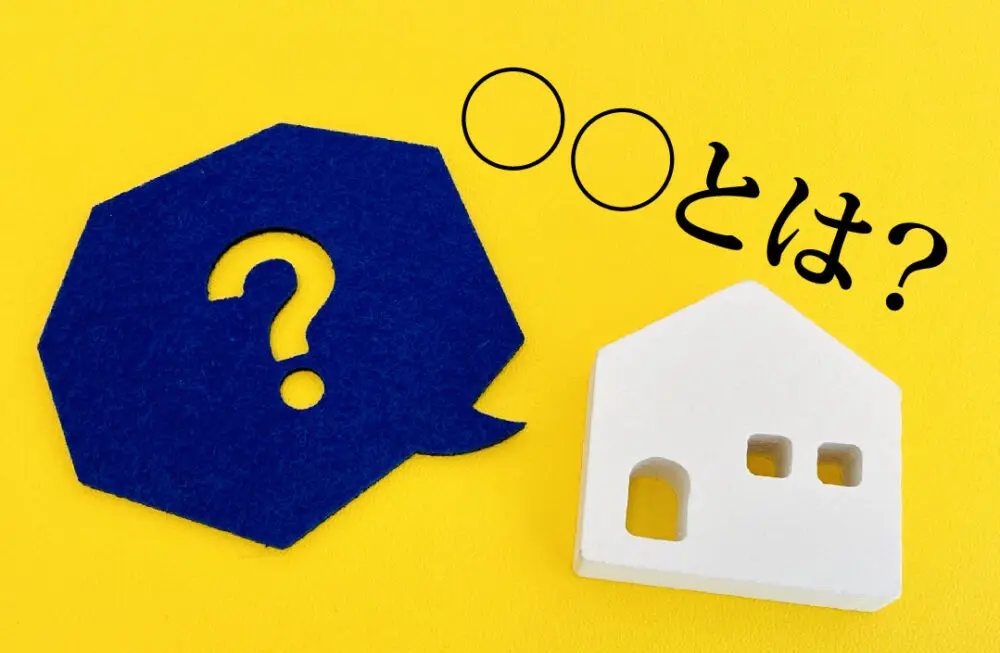



コメント